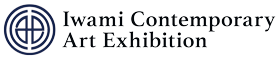KIM SONG-DONG

《略 歴》
-
兵庫県生まれ 1950-2016
-
2007年青島国際アートフェスティバル
(青島・中国) -
2009年柿衞文庫開館25周年記念展
(柿衞文庫・伊丹) -
2012年霊岩郡立美術館開館記念展
(全羅南道霊岩郡・韓国)
《パブリックコレクション》
-
ロックフォード大学(米国)
カボ・フリオ国際版画ビエンナーレ(ブラジル)
青年美術家協会(ハンガリー)
光州市立美術館(韓国)
霊岩郡立美術館(韓国)



展示会場
Studio652
キム・ソンドンの「Intervene」
天野和夫
白いベールを通して見える花嫁の顔は、初々しさにあふれている。キム・ソンドンの作品を初めて見たときに、わたしはそう思った。次に思い起こしたのは、障子に映る影だった。物そのものがそれなりに見えるよりも、何かを介在させることによって、より美しく見えることがある。近くサンフランシスコでの滞在に終止符を打って、日本での生活を始めるという手紙を彼からもらって、その準備に一時帰国をした彼が携えて来た作品は、アメリカと言えば抽象表現主義という私の常識に当てはまらない作品だった。彼は私がすぐさま個展の承諾をするものと思っていたらしい。のちになって、彼は何度か私の決断が遅いとなじったことがあったが、それはひとえに私の彼に対する理解不足が原因だった。
幼児は、小さな石ころに典味を持つ。自らが生まれ出たルーツを追いかけるように。しかも視覚よりはむしろ触覚を最大限に働かせる。必要なら、口に入れさえもする。石ころと自分の間に介在するもろもろの事象を、これでもかというほどにつかみ取ろうとする。石ころは宝物だ。
キム・ソンドンが描く対象は、小さなものが多い。コップであったり、種であったり、時にはくしゃくしゃになったティッシュペーパーであったりする。すべて触覚に起因する対象物だ。それらを、大きな画面の中で、小さく小さく扱う。画面のほとんどが、それらを取り巻く空間だ。それを静物画として見ることはできる。シャルダンやセザンヌ、その他の静物画の巨匠たちと変わらないのは、描かれた静物自体の美しさではなく、その背後にある「何か」を描こうとする点だ。ただ、違うのは、対象物を顕在化させるのではなく、薄い紙で覆うことによって、シルエットにしてしまうことにある。知覚による顕在化とは逆の方向で事物を処理し、まわりの空間に溶け込ませてしまう。顕在化が理性に依る所作であるとすれば、彼の方法論は感覚による非顕在化とでも言えようか。まるで、幼児体験に引き戻されるかのようだ。
彼のこの方法論が、どこで確立したかは定かでない。サンフランシスコで制作した作品のほとんどはコラージュによるイメージの合成であった。往時の制作でも用いたチャイナ・コラージュ(薄紙で覆って、その上から別のイメージを苔き加える技法)が、いつしかその最も効果的な表現方法として変化したものであろうということは想像できる。その契機となったものが、アメリカのポップアートとの出会いであったのだろう。だから、抽象表現主義とは一線を画している。
キム・ソンドンの「空間の中における事物の非顕在化」は、Interveneという単語に集約され、ほとんどの作品に彼が好んでタイトルの頭に用いている。薄紙が介在することによって、事物の原初的な存在がはっきりするという彼のコンセプトを示している。
このコンセプトに、実は彼は飽き足らないものを感じていたフシがある。2000年前後に、いきなり陶芸の世界に踏み込んだのは、薄紙の介在から火の介在に視点を移したからではなかったか。残念ながら、その後の展開を例示する作品が希少なために、このことの論証は極めて難しい。
いずれにせよ、触覚から出発した彼の作品は、触覚がもとめる「やさしさ」にあふれている。私たちが彼の絵に魅力を感じるとすれば、実は彼の「やさしさ」に魅力を感じているのかもしれない。
(天野画廊画廊主)